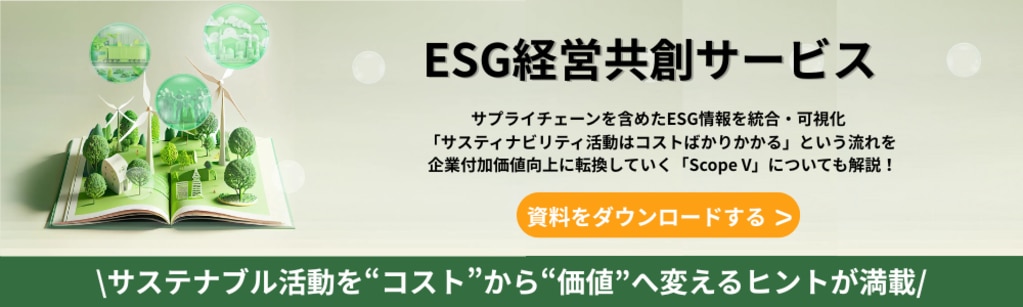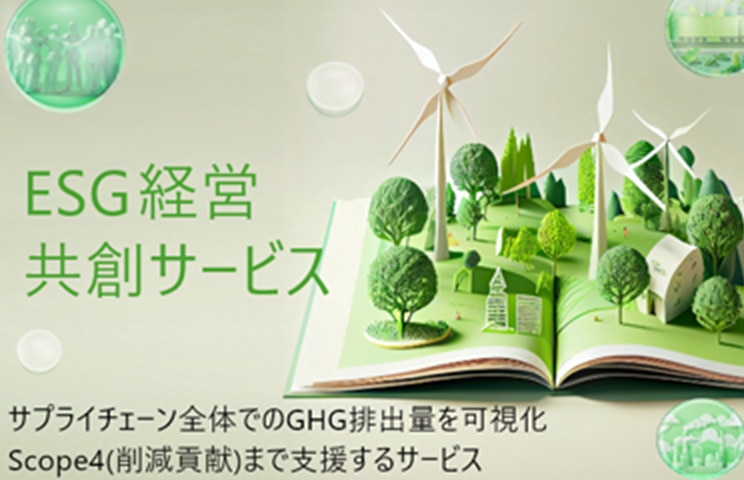環境教育とは?教育の目的と必要性、主なテーマや取り組み例を解説
地球温暖化や生物多様性の喪失など、環境問題が深刻化する中で、持続可能な社会の実現に向けた鍵として注目されているのが「環境教育」です。
近年では、脱炭素経営やESG投資への対応が求められる中、企業にとっても環境教育は単なる社会貢献にとどまらず、持続可能なビジネスを支える重要な基盤となりつつあります。
本コラムでは、環境教育とは何か、その目的と必要性、学ぶべきテーマについて、わかりやすく解説します。
環境教育とは?
環境教育とは何か?意味や定義を解説
環境教育とは、地球環境の現状やさまざまな環境問題について学び、持続可能な社会を築くために必要な知識や行動力を身につけるための教育です。
環境省では、環境教育を「人間と環境とのかかわりについて理解と認識を深め、責任ある行動がとれるよう、国民の学習を推進すること」と定義しています。
環境教育の目的と背景「環境保護教育の重要性」
環境教育の主な目的は、環境の現状や課題を正しく理解し、環境保全活動に積極的に取り組むことで、持続可能な社会の実現を目指すことにあります。
この背景には、1992年の地球サミットを契機とした、「持続可能な開発(Sustainable Development)」という考え方が広まり、環境教育はその実現に欠かせない要素として位置づけられるようになりました。また、日本では環境基本法や環境教育推進法により、国や自治体、学校、企業などさまざまな立場で環境教育の取り組みが進められています。
環境保護教育は知識の習得にとどまらず、課題のための批判的思考を育て、行動につなげることで、環境保全に貢献できる人材の育成することも目的としています。
環境教育の意義と必要性
環境教育は、個人や社会全体が環境問題に対する理解を深め、持続可能な社会を実現するために必要な行動を促す重要な教育の一環です。環境問題は、私たちの日常生活だけでなく、企業活動や国際社会にも大きな影響を与える深刻な問題となっています。
これらの課題に対応していくためにも、環境教育が不可欠となっています。
日本ではいつから実施されているか?
日本で環境教育が本格的に広まったのは、1970年代の公害問題や環境汚染への関心の高まりがきっかけです。当初は学校や地域による自主的な取り組みが中心でしたが、1990年代以降、国際的な環境保護の動きと連動する形で制度の整備が進みました。1993年には環境基本法が制定され、2003年には環境教育推進法が施行されるなど、国の政策として明確に位置づけられるようになりました。
こうした法整備を背景に、学校教育だけでなく地域社会や企業活動の中にも環境教育が広がり、現在では持続可能な社会の実現に向けた重要な柱となっています。
環境教育の主なテーマ・学習内容
環境教育の主なテーマは、地球規模の問題から身近な生活環境まで幅広く設定されています。下記に代表的なテーマと学習内容について記載いたします。
主なテーマ | 学習内容 |
地球温暖化・気候変動 | 温室効果ガスの排出や気温上昇の影響を学び、気候変動の対策として省エネや再生可能エネルギーの活用を理解する。 |
生物多様性の保全 | 絶滅危惧種や生態系のつながりについて学び、自然との共生の重要性を理解する。 |
公害・環境問題 | 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染などの環境問題の歴史と現状について学び、地域や健康への影響を理解する。 |
資源循環 | 資源の有限性について学び、ごみの分別や削減を通じた持続可能な資源利用を理解する。 |
持続可能なライフスタイル | 日常生活における省エネ、節水、エコ商品の活用について学び、持続可能な暮らし方を理解する。 |
自然体験・環境とのふれあい | 企業活動と環境の関係について学び、環境配慮型の生産やCSR・ESG経営の重要性を理解する。 |
産業と環境 | 環境に配慮した生産やCSR、ESG経営など、ビジネスと環境の関係について理解する。 |
SDGs | SDGsと環境教育のつながりについて学び、気候変動や生態系保全に関する国際的な目標を理解する。 |
ESD | 持続可能な社会を実現する力(価値観・知識・行動力)を育てる。 |
地球温暖化と気候変動
地球温暖化の原因となる温室効果ガス(CO₂やメタンなど)の排出メカニズムや、その影響としての気温上昇、異常気象、海面上昇などについて学びます。さらに、気候変動に対する対策として、省エネの実践や再生可能エネルギーの活用など、日常や社会の中でできる取り組みについて理解を深めます。
生物多様性の保全
生態系の仕組みや生物同士のつながりを通して、自然と人間の関係について学びます。絶滅危惧種の存在や外来種の問題、森林伐採や都市開発による生物多様性の喪失について理解を深め、自然との共生の在り方を考えます。
公害・環境問題
日本の公害の歴史(四大公害病など)を通じて、環境汚染が人の健康や地域社会に及ぼす影響について学びます。また、現代における大気汚染、水質汚濁、マイクロプラスチックなどの新たな課題も取り上げ、環境問題に対する社会的責任や法制度の役割について理解を深めます。
資源循環(3R:リデュース・リユース・リサイクル)
ごみの発生から最終処分に至るまでの過程を学び、資源が有限であることを理解します。そのうえで、3R(リデュース=削減、リユース=再使用、リサイクル=再資源化)の考え方に基づいたごみ減量の方法を学び、持続可能な資源利用に向けた行動を考えます。
持続可能なライフスタイル
私たちの生活が環境に与える影響を振り返り、エネルギーや水の使い方、商品選び、交通手段など、日常の行動を見直す視点を養います。カーボンフットプリントやライフサイクルアセスメント(LCA)の考え方を通じて、持続可能な暮らし方を学びます。
自然体験・環境とのふれあい
自然観察や野外活動などの体験を通じて、五感で自然の豊かさや大切さを実感します。自然にふれることで興味や愛着を育み、環境保全に対する主体的な行動につながる感性と姿勢を養います。
産業と環境(企業活動とサステナビリティ)
企業の経済活動が環境に与える影響について学び、環境配慮型の生産・流通・消費のあり方を理解します。CSR(企業の社会的責任)やESG(環境・社会・ガバナンス)といった観点から、持続可能なビジネスの在り方や、消費者としての責任ある選択について考えます。
SDGs(持続可能な開発目標)との関連
国連が掲げるSDGs(持続可能な開発目標)の中でも、特に環境に関連する目標(例:目標13「気候変動対策」、目標15「陸の豊かさも守ろう」など)を中心に学びます。自分の行動が地球規模の課題解決につながることを理解し、グローバルな視点とローカルな実践を結びつける力を育てます。
ESD(持続可能な開発のための教育)
ESD(持続可能な開発のための教育)はEducation for Sustainable Developmentの略で、気候変動や貧困など現代の地球規模の課題を自分ごととして考え、行動を通じて持続可能な社会の実現を目指す教育です。
「Think globally, act locally(地球規模で考え、足元から行動する)」を基本に、未来の世代のために新しい価値観や行動を育むことを目的としています。
当社が考える環境教育の問題点
ESDの国際的な展開と「ESD for 2030」
いま、世界は気候変動や資源の枯渇、貧困、格差といった複雑な課題に直面しています。こうした問題に立ち向かうために、私たち一人ひとりが「持続可能な社会の担い手」として学び、行動することが求められています。そのための学びが、ESD(持続可能な開発のための教育)です。
このESDは、2002年に日本が国連で提案し、国際的な教育運動として発展してきました。
2005年からの「国連ESDの10年」、続く「グローバル・アクション・プログラム(GAP)」を経て、いまは新たな枠組み「ESD for 2030」が動き出しています。
しかし、「ESD for 2030」が描く理想を実現するには、いくつかの課題もあります。たとえば、「ESDの大切さは理解されていても、教育現場での実践が追いついていない」「教える先生方の知識や教材が不足している」といった現実があります。また、ESDを進めるための資金や人材の確保も課題です。
だからこそ、学校、家庭、地域だけでなく、企業も重要な担い手としての役割が期待されています。企業は、環境に配慮した製品づくりやサステナブルな経営(CSR・ESG経営)を通じて、社会全体に影響を与える存在です。
たとえば、下記のような教育と社会の橋渡し役としても大きな貢献ができます。
- 環境教育への協力(企業側の実態説明 や職場見学)
- 若者の学びを支えるインターンシップや実践の場の提供
- 社員のリスキリングや生涯学習支援
持続可能な社会の実現には、すべての世代・立場の人々が連携することが不可欠です。
企業が教育と結びつきながら、次世代の育成を担うことは、社会貢献であると同時に、未来のビジネス基盤を築くことにもつながります。
未来をつくる力を育む「ESD for 2030」。その実現には、私たち一人ひとり、そして社会のあらゆる組織の協力が必要です。
持続可能な社会を支える教育の役割
環境教育における重要な課題として、以下の3点に焦点を当ててご紹介しています。ぜひ参考にご覧ください。
- 消費者行動変容の必要性: 環境に配慮した選択が、消費者の経済的負担とならないような意識改革の重要性。
- 日本と欧州での意識格差: 欧州に比べて、日本では「自分一人が動いても変わらない」という意識が根強い現状と、その背景にある教育の違い。
- 若年層のSDGs認知と本質理解: 中高生の間でSDGsの認知度は高いものの、その本質的な意味や具体的な行動への繋がりに関する理解を深める必要性。
「ESG経営共創サービス」の環境教育活動
ESG経営共創サービスの概要
「ESG経営共創サービス」は、フューチャーアーティザンが提供するESG特化型コンサルティングサービスです。
ESG経営における戦略立案から施策実行、情報開示支援までワンストップで対応。企業のステージや課題に合わせて、最適なプランを提案します。