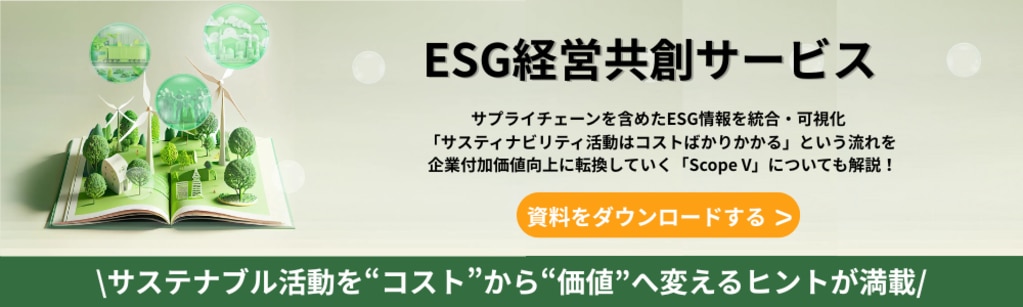製造業のESG課題解決の実践|梅原由美子氏と語る具体的な施策
昨今、企業がESG経営を競争の中で推進する必要性が高まる中、新たにサステナビリティ推進室などの部署を立ち上げ、情報開示を行うケースが増えています。しかし、体制だけが先行し、担当者が十分に育たないまま業務を担うケースも多く、結果として「やらされ感」を抱えながら孤軍奮闘している姿が見られます。こうした状況では、人材の育成が喫緊の課題となります。
このようにESG経営を具体的に実践する時に必ず伴う、人材育成、ESG経営のゴールや価値評価といった取り組みを具体的にどのように実践すれば良いのか?弊社ESG事業責任者の大江隆徳とESG分野の先駆者でありプロフェッショナルのValue Frontier 株式会社 代表取締役の梅原由美子氏が議論します。
なぜ「ESG推進」が現場で孤立してしまうのか?
大江:サステナビリティ推進室を新設したり、情報開示の準備を始める企業が増える一方、「誰も教えてくれない中で孤軍奮闘している」という声も多く聞こえてきます。実際、部署ができたものの、目標も支援もないまま、担当者が「やらされ感」を抱えてしまうことが多い。まずはその構造自体に課題があると感じます。
梅原氏:それは私も実感します。もともとCSRや環境対応は専門部署が担っていましたが、いまは経営企画部門や新設のサステナビリティ部門が、非財務情報の開示を軸に「全社的な視点」で求められるようになってきています。ただ、情報開示の必要性ばかりが先行し、開示された情報をどう経営や人材育成に活かすかの部分が、まだまだ追いついていません。
まずは、サステナビリティ経営のゴールを設定し、その達成に向けて必要となる人材をどのように育成するかを検討する必要があります。
「未来を描く力」を育てる教育こそ、ESGの基盤
大江:私たちフューチャアーティザンでは、若い世代に未来の社会や自分たちの仕事の意味を考えてもらう探究型教材を開発しています。企業の課題を当事者として捉え、自ら仮説を立てて答えを出す──そういう力を育てることが、結果としてESGの担い手育成につながると考えています。
梅原氏:とても良い取り組みだと思います。私たちも東京都と「DoNuts Tokyo」という若者向けゼロエミッション教育プロジェクトを運営しています。企業と若者が直接対話する場を設けることで、企業側も若い人たちの真剣なまなざしに刺激を受け、むしろ学ぶ側になる瞬間もあります。MITのピーター・センゲ博士も述べているように、サステナブルな社会の実現には「次世代の視点」「構造の変革」「新しい発想」が必要です。まさに教育の場がそれを体現しています。

ルールをつくる側に回る─日本の可能性と里海モデル
梅原氏:日本の製造業には、国際的なルールメイキングにもっと関与してほしいと感じています。
たとえば岡山県の中小企業が展開した「廃貝殻を活用した人工漁場」の技術。これは地域の自然共生思想=“里海”とセットでメキシコに輸出され、国レベルの政策にも影響を与えました。
自然資源の利用と保全を両立させるこの思想は、欧米にはない発想です。ルールに従う側ではなく、「思想と技術をセットで提案し、ルールにしていく」発信力が今後の日本企業に求められていると思います。
大江:私も「日本の考え方ごと持ち込む」という視点には大きな可能性を感じます。ルールを押し付けられるのではなく、“提案する”ことで結果的にそのルールをつくっていく──そのくらいの気概を持つべきだと強く感じました。
データ開示の壁は「現場との分断」にある
大江:情報開示をしようにも、データは工場や現場にあります。ところが、現場からすると「なぜ新たな業務が増えるのか」「何に使われるかわからない」という不信感も強い。本社と現場の意識差は、いまや多くの製造業で顕在化しています。
梅原氏:そのとおりです。ある大手企業では、グローバル拠点も含めた開示プロジェクトを3年かけて推進しました。最初は「なぜ出すのか」の説明から始まり、拠点ごとの教育と社長の現地訪問を繰り返すことで、ようやく“自分ごと”として浸透していった。教育とトップの巻き込みがセットでなければ進みません。
生成AIも実証段階に─「開示コスト1/10」も実現可能
大江:私たちも、情報開示に必要な作業をテクノロジーで10分の1に効率化した事例があります。これからは、テクノロジーで作業を省力化し、人は価値判断や戦略策定に注力する時代。生成AIによるスコープ1,2,3の自動分類の実証も進めており、精度も実用に近づいています。
梅原氏:GXとDXは密接に関係しています。サプライチェーン全体で正確なカーボン算定をするには、企業間をまたぐデータ収集が必要です。その中でDXで得た仕組みや知見をGXに活かす──このサイクルが、企業にとってもESG推進の現実解になるはずです。

「環境情報」を価値へと転換するには
梅原氏:ESGは「コストをかける活動」ではなく、「価値を創る行為」であるべきです。たとえば、カロリー表示のように、製品にカーボンフットプリントが表示されれば、消費者が環境配慮型商品を選びやすくなります。それが売上やブランド価値に結びつく。こうした構造を企業自ら設計していく必要があります。
大江:自動車部品メーカーと進めているCO2ラベリングの取り組みでは、部品ごとに排出量を可視化し、「環境配慮型GXブランド」として展開しています。これを取引先や消費者が評価してくれるようになれば、まさに“選ばれる理由”になるはずです。
消費者が変われば、価格も変わる
梅原氏:カーボンプライシングが進めば、環境に配慮しない商品には追加コストが課されるようになります。それに対抗するには「高くても納得できる理由」が必要。長寿命設計や修理可能性、循環型設計といった“価格に見合う価値”が求められます。いま、CtoCプラットフォームでの再流通は増えていますが、今後はメーカーや小売も巻き込んだ再資源化のエコシステムが必要です。それが企業のブランディングにもつながっていくでしょう。
ESGの“主語”を増やすために
大江:ESGの現場では「やらされ感」を乗り越え、「自分の言葉で語れる人」をどれだけ増やせるかが鍵です。そのためには、教育・対話・仕組みづくり・見える化という多層的なアプローチが必要です。
梅原氏:そうですね。そしてそのすべては、「自分たちが生きていく未来を、どうデザインするか」という問いとつながっています。技術だけでも、制度だけでも足りない。そこに“人”が介在するからこそ、ESGは価値を持つのだと感じます。
大江 隆徳(おおえ・たかのり)|フューチャーアーティザン株式会社 ESG事業責任者
メーカーの設計・製造領域におけるデジタル変革支援を多数手がけ、近年はESG・GXに関する製造業支援プログラムの立ち上げに注力。技術と経営の接続を支援する伴走型のコンサルティングを提供している。生成AIやデータ整備による業務効率化など、テクノロジー活用の実践知に強み。
梅原 由美子(うめはら・ゆみこ)氏|Value Frontier 株式会社 代表取締役/ESG・サステナビリティ戦略コンサルタント
企業のESG戦略・人的資本経営支援を専門とし、サステナビリティ情報開示・評価・人材育成に豊富な実績を持つ。東京都や環境省をはじめとする行政・自治体と連携した次世代教育や、国際的なルールメイキングへの提言活動も行っている。
※プロフィール出典:https://honkicom.com/about/umehara
#1 ESG経営を動かすのは誰か─製造業に求められる人材育成と次世代との共創
#2 ESGを価値に変える実践力─製造業が進むGX経営の肝「評価・価格・意識をどう変えるか